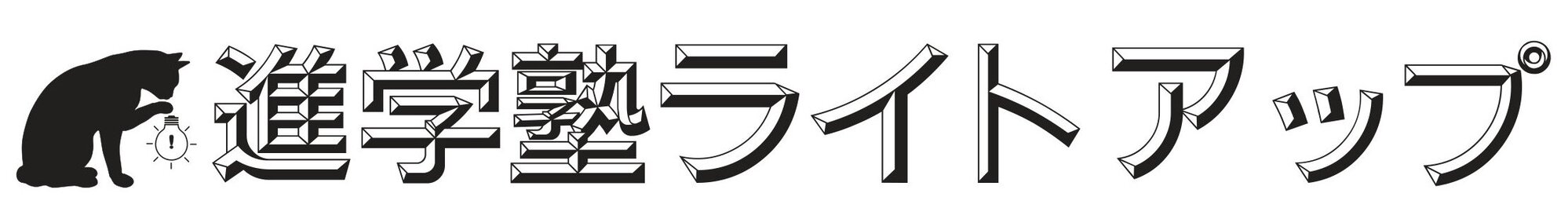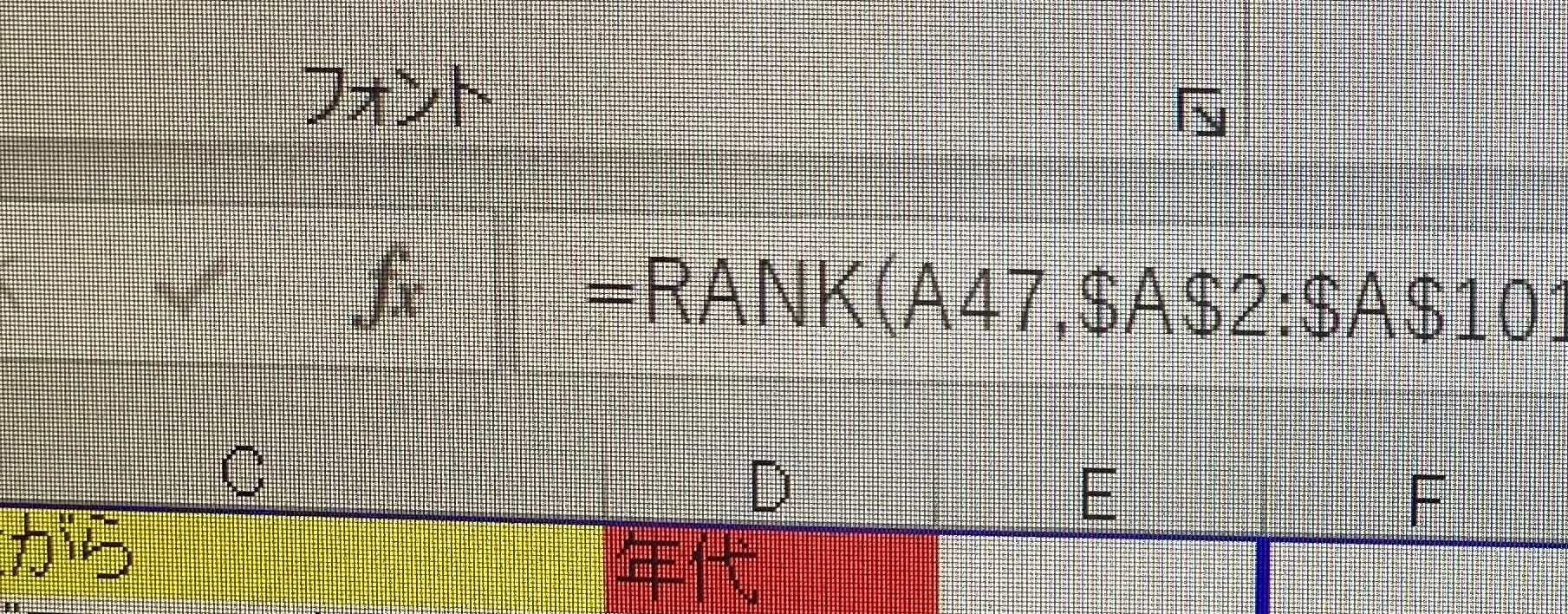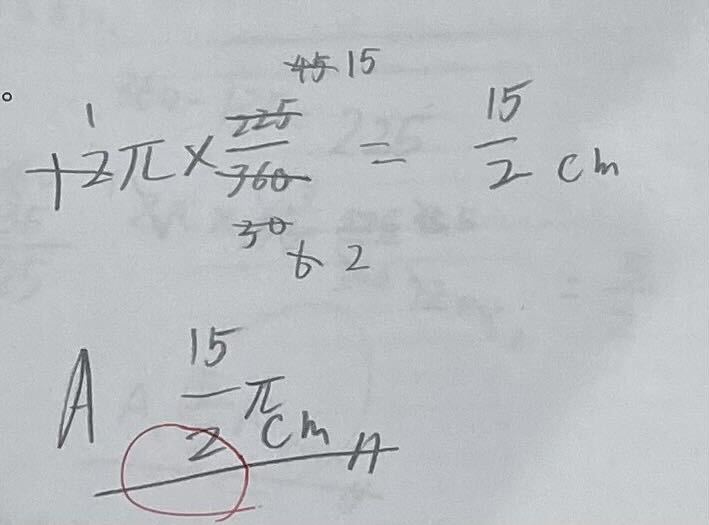【雑談】あらためて考える子育てのあれこれ
みなさん、こんにちは!進学塾ライトアップ、代表の西川です。
1/21土は10時から、1/22日は14時から教室を開けます。1/23月はお休みですので、ご注意ください。
私事で恐縮ですが、我が子が生後2か月になりました。

先日、生後2か月を過ぎると受けられる予防接種が4種類あるということで、我が子を連れて病院に行ってまいりました。(ちなみにこちらの予防接種は補助が出ているので無料です。)
先に処置を終えた、注射を打たれた他の赤ちゃんたちがぎゃんぎゃん泣いているところ、いよいよ我が子の番になりました。あまり泣かないように寝かせていたところに急に一発目の注射を打たれたので、ほんの1,2秒の間があきました。・・・が、あとは他のお子さんと同じ。3本目の注射を打つ頃には顔を真っ赤にして泣き叫んでいたのですが、打ち終わって処置室を出た瞬間に爆睡!笑
なんということでしょう! 我が子の神経の図太さというか、たくましさに感心してしまいました笑
今までは、目も合わないしこちらがあやしてもほぼ無反応の状態でしたが、最近は「あう」とか「へへっ」などと声を出したり、嬉しいことがあると笑顔になってくれるようになって、帰宅後にも仕事の疲れが吹っ飛んでいます。
そして、子どもが出来てからというもの、普段以上に子育てというワードに敏感になり、色々と情報を集める機会が増えました。
今回はそこからいくつか気になったものを雑多に紹介していこうと思います。
子どもと親の距離感のお話
埼玉県川越市にある塾の先生のブログに、「なぜ子供の成功を願ってあれこれ動く親ほど失敗するのか」という記事があります。
子どもが「自分が〇〇がしたい」という自我が芽生えてきたら、親は少しずつ「やってあげる」から「見守る」にシフトしないといけない、そうしなければ、親は「子供が言うことを聞いてくれない」と嘆き、子供は「親がウザイ」となって、お互いが幸せではなくなるというお話でした。日々お子さんと闘っているご家庭には、何かヒントになるものがあるかもしれません。
それと関連して、埼玉県さいたま市にある別の塾の先生のブログには「子育て四訓」と呼ばれるものがありました。
子育て四訓
乳児はしっかり肌を離すな
幼児は肌を離せ手を離すな
少年は手を離せ目を離すな
青年は目を離せ心を離すな
自立・自走に向けて間合いの取り方を。
https://www.yu-hikai.com/blog/12893.html
この二つのブログの内容に共通しているのは、あれもこれも危ないからダメ!やらせない!とするのではなく、逆に、あれもこれも全部やってあげる!とするのでもなく、適切な距離感で、時には見守ってあげたり、特に口にも出さず何か困ったときには手を差し伸べるくらいの距離感でいてあげるのが、子供にとって良い関係性だということですね。
私が読んでいる子育て本の中にも、それに関連するようなことが書いてあったように思います。
うちの子にとってはまだまだ先の話になりますが、赤ちゃんがつかまり立ちをするようになるきっかけとして、「おもちゃをつかまり立ちしないと届かない場所に置いておく」というのが良いらしいんですよね。子どもがねだるからおもちゃを取ってあげる、あるいはおもちゃを手のすぐ届くところに置いてあげるという風にしておくと、赤ちゃんがわざわざ苦労してつかまり立ちをしようとは思わないのだそうです。「興味・関心」を持ち、自分で「選択」をし、その結果に「満足感」を得るというサイクルを作ってあげなければいけません。
これはもちろん、つかまり立ちに限った話ではないのではないかと思います。親が子供のことを全て決めてしまえば楽かもしれませんが、そうすることで子供は何かを自分から行動しようと思わなくなるかもしれません。考えることをやめて、とりあえず誰かが言う通りにしておけば怒られないと考えるようになるかもしれません。自己肯定感が低くなってしまうかもしれません。
我が子がかわいくて仕方ないからこそ色々とやってあげたくなる気持ちというのは、私も今ならものすごく分かるのですが、私もぐっとこらえようと思いますし、中学生の生徒さんたちには勉強をするのかしないのかも含め、きちんと自分で考えて行動できるようになってほしいです。
子どもは大人の鏡
ドロシー・ロー・ノルト博士が作った親子についての詩ですが、こちらは、4年前の開校以来、ずっと塾のロッカーに貼ってある私の好きな詩です。これも人の親になってから見返すと、また色々と思うところが出てきます。
『子どもは大人の鏡』
子どもは、批判されて育つと
人を責めることを学ぶ子どもは、憎しみの中で育つと
人と争うことを学ぶ子どもは、恐怖の中で育つと
オドオドした小心者になる子どもは、憐れみを受けて育つと
自分を可哀想だと思うようになる子どもは、馬鹿にされて育つと
自分を表現できなくなる子どもは、嫉妬の中で育つと
人をねたむようになる子どもは、ひけめを感じながら育つと
罪悪感を持つようになる子どもは、辛抱強さを見て育つと
耐えることを学ぶ子どもは、正直さと公平さを見て育つと
真実と正義を学ぶ子どもは、励まされて育つと
自信を持つようになる子どもは、ほめられて育つと
人に感謝するようになる子どもは、存在を認められて育つと
自分が好きになる子どもは、努力を認められて育つと
目標を持つようになる子どもは、皆で分け合うのを見て育つと
人に分け与えるようになる子どもは、静かな落ち着いた中で育つと
平和な心を持つようになる子どもは、安心感を与えられて育つと
自分や人を信じるようになる子どもは、親しみに満ちた雰囲気の中で育つと
生きることは楽しいことだと知る子どもは、まわりから受け入れられて育つと
世界中が愛であふれていることを知るあなたの子どもはどんな環境で育っていますか?
https://www.php.co.jp/books/dr.php
私は我が子に、平気で嘘をついたり、他人の嫌がるようなことをするような子になってほしくありません。誠実で周りの人から信頼される子になってほしいと強く願っています。そのためには、まず自分の態度をきちんと改めなければならないということをこの詩を読むと強く感じます。
他人に対して、乱暴な態度をとっていないか、誠実な対応をしているのか、我が子も生徒たちも含め、子供がそれを見て真似をしてもいい行動をとれているのか、ちゃんと自問自答していきたいと思います。
やはり気を付けておきたい「子どものスマホ依存」
「スマホ依存で1日2時間の勉強がムダに!ゲームが子どもの脳に及ぼす影響」
子どもたちの知的発達にかかわる問題として、ゲームが取り沙汰されることが多い。電車に乗っていると、スマホでゲームに熱中している人をよく見かける。それも、子どもではなく大人を見かけることも多い。子ども時代、あるいは若い頃から習慣になっているのかもしれない。ゲームには、神経伝達物質ドーパミンを放出させ脳を興奮させる効果があるため、中毒性が高く、依存症を引き起こしやすいと言われる。
(中略)
大人も依存症に陥るほどなのだから、まだ自己コントロール機能を担う脳の部位の発達途上にある子どもが依存症に陥るリスクは非常に大きい。
(中略)
脳科学的手法で認知機能の発達を研究している川島隆太と横田晋務たちの研究グループは、5歳から18歳の子どもや若者を対象に、3年間の間隔を空けて脳の画像を撮影し、知能も測定して、ゲームをする時間が脳の形態や認知機能に与える影響について検討している。
その結果、ゲームをする時間が長いほど、語彙力や言語的推理力に関連する言語性知能が低いことが明らかになった。
また、驚くべきことに、長時間ゲームをする子どもの脳は、脳内の各組織の発達に遅れがみられることがわかった。脳画像からは、記憶や自己コントロール、やる気などを司る脳の領域における細胞の密度が低く、発達が阻害されていることが明らかになった。
さらには、ゲームで長時間遊んだ後の30分~1時間ほどは、前頭前野が十分働かない状態にあり、その状態で本を読んでも理解力が低下してしまうということを示すデータも報告されている。ゲーム中には、物事を考えたり自分の行動をコントロールしたりするのに重要な役割を担う前頭前野の血流量が少なくなり、機能が低下してしまうのだろうという。
(中略)
ゲームで長時間遊んだ後の30分~1時間ほどは、前頭前野が十分働かない状態にあり、その状態で本を読んでも理解力が低下してしまうことがデータによって示されている。ゆえに、勉強をしても頭に入らない。
https://diamond.jp/articles/-/274045
こちらの記事は、一昨年の6月に掲載されたものですが、以前私が紹介した『スマホ脳』の話でも同様の話をさせてもらいました。(念のため、下にリンクを貼っておきます)
やはり、スマホに関しては、「寝室・トイレには持ち込み禁止」など、ご家庭できちんとルールを決めて頂くのは、今の時代は絶対に必要なことのようです。特に、勉強やスポーツなどで本来目標にしていることに支障が出てしまう場合には、スマホやSNSやゲームからは距離を置く「デジタル・デトックス」をしていただく必要があるかもしれません。
もちろん、スマホでやるゲームにもリフレッシュの効果もあるでしょうし、ゲームから知識を得ることだってあるでしょう。しかし、子供に自由にスマホを持たせていて依存症になってしまったのでは、その子の勉強やスポーツをやる際の集中力ややる気にも影響が出てしまうということです。
すでにその兆候があるご家庭であれば、しっかりと家族会議を開いて、改めてスマホに関するルールを話し合うべきかと思います。もちろん、ただ「ダメ!」というのではなく、「スマホを使いすぎると集中力とやる気がうばわれちゃうから、友達と遊ぶことすらもスマホによって楽しめなくなるんだよ。それでもいいの?」と、理由をきちんと説明してあげることが大切だと思います。
まとめ
まだまだ話したりないこと、というより、ご紹介したいことは色々あります。
今回ご紹介している話は個人塾の塾長先生方のグループラインで話題にのぼっているお話が中心ですが、本当に先生方のすごさを日々感じています!
「学力が高いお子さんの親御さんに、かなりの確率で共通しているのは〇〇」
「今の時代、子供にとって本当に必要なのは学力・学歴よりも〇〇」
といったお話、こちらもちゃんと私自身の頭の中を整理して、ちゃんと時間を作ってお伝えしたいと思っています。
色々と周りから教えてもらった情報の中でも、自塾に活かせるものは今後も積極的に取り入れたいと思っています。
引き続きよろしくお願いいたします!